
海から山へ、そして再び海へ ─ 一本の道がつなぐ物語
カツオトレイルは、静岡県焼津市を起点に、静岡市、藤枝市、島田市を経て、南アルプスの南端・川根本町へと向かう総距離205km・獲得標高6,150mの壮大な周回ルートだ。
このプロジェクトを立ち上げたのは、『PAPERSKY』編集長であり、日本各地の街道を歩き続けてきたルーカス・B.B.とその仲間たち。これまでルーカスは長い時間をかけて旧東海道をはじめ、中山道、鯖街道、奥の細道、塩の道など、古くからの道を実際に歩き、その魅力を国内外へと発信してきた。
そうした日本の古道や旧道を歩く経験と、「歩くことは学ぶこと」という新しいコンセプト”TRAIL LEARNING”※を基盤に構想されたカツオトレイル。静岡の自然環境だけでなく、漁業文化や歴史、大井川流域の独自の風土まで、地域固有の文化資源に触れられるロングトレイルとして設計されている。
2026年のグランドオープンを目指し、2025年春からはセクション1を皮切りに順次開放される予定だ。

ハンモック泊の可能性を探る視察旅

今回の視察には、JMW(Jindaiji Mountain Works)代表のジャッキーさんとスタッフの森さんを迎えた。JMWは、日本のウルトラライトハイキング黎明期から活躍してきたインディペンデントアウトドアメーカーで、近年はハンモックを活用したハイキングやバイクパッキングのスタイルを提案している。
少しでも軽い装備で自然との繋がりを感じながら山で過ごしたいULハイカーのために開発されたPBハンモック。全長280cm、幅130cmという少し大きめのサイジングながら、本体重量はわずか180g。このハンモックとタープを組み合わせたシステムで、軽量かつ快適なハンモック泊を可能にした。
ULハイカーやバイクパッキングで注目されるハンモック泊だが、場所を選ばずに設営できる利便性がある一方で、国内の登山文化ではまだ少々“グレー”とされている節もある。これは、日本の山岳地帯に根付く「山小屋文化」や「テント指定地」といった長年のルールとの整合性が関係している。
海外のように“自己責任と分散キャンプ”が前提の文化とは異なり、日本では原則として指定地以外での宿泊が認められていないため、自由な設営スタイルがルール外と見なされやすいのだ。
また、ハンモック泊自体がまだ新しいスタイルであり、明確な基準が整っていないため、「禁止ではないが、明確に許可もされていない」という“理解の過渡期”にある。
しかし、ULハイカーやバイクパッカーの間で関心は高まりつつあり、環境への配慮とともにルール形成が進めば、今後はより自然と共存する新たな宿泊スタイルとして受け入れられていく可能性がある。
そこでカツオトレイルでは、オフィシャルにハンモック泊が可能なスポットを整備する計画を、JMWの監修のもと進めている。今回はその候補地選びと運用方法の監修をジャッキーさんたちに依頼し、実際に現場を歩いて確認する──それが今回の視察ツアーの目的だった。
そして、渓流釣りをすることは言うまでもない。狙いはアマゴだ。


視察が遊びに変わる瞬間
コースに隣接するキャンプ場や、水場・トイレを確保できる候補地を巡りながら、私たちは実際にハンモックを張り、設営方法やレイアウト、同時に設営できる本数を一つひとつ確認していった。トレイルの一部では、宿泊場所の問題で5km程度の遠回りが必要な箇所があるのだが、ハンモックを活用することでそれをショートカットできる。ハンモック泊のメリットは大きい。
まだ地元への説明や許可の関係などクリアしなければならない課題もあるが、日本初であろうハンモック泊で回れるロングトレイルを目指して進めていく。

候補地を見て回るだけでなく、実際にカツオトレイルの一部を歩き、その全体像や雰囲気を体感してもらうことも大切だった。セクション4の千頭から奥大井湖上駅へ抜けるルートは、ブナの林が続く美しい区間。ローカルトレイルの奥深さと豊かさを十分に実感できる場所だった。山々に囲まれた湖上にぽつりと浮かぶような奥大井湖上駅は、クールジャパン・アワード2019も受賞した注目のスポットでもある。

駅にかかるレインボーブリッジを渡り、ちょうどカツオトレイルの中間地点にあたる長島ダムの湖畔を、この日の野営地に選んだ。林の中にハンモックを張り、眼下に広がる静かな湖面を眺めながら過ごす。夕食は地元の鹿肉とお酒。色とりどりのハンモックが森の中でゆらめき、視察という名目で始まった一日は、次第に特別な時間へと姿を変えていった。

そして翌日は、カツオトレイルから少し外れて南アルプスの渓流へ。狙うのは、美しいアマゴだった。


渓流にて、未来を思い描く
翌朝は快晴。ハンモックを撤収し、この日は狙いを定めた川へ車を走らせた。入渓地点まで少し歩き、一気に谷を下る。そこは地元でも人気の渓流で、比較的入渓しやすい分、先行者の姿も見えた。魚の反応は薄く、思うような釣果にはつながらない。


それでも、いつもなら見切ってしまう小さなポイントにまで丁寧にフライを流していくジャッキーさんと森さん。テンカラを雰囲気のあるレーンに流し続けるルーカス。水の流れる音や、木々の風に歪む音、鳥たちの囀り。ゆったりとした速度で渓流を歩きながら、自然と会話はカツオトレイルの未来に及んでいった。

「歩くだけでなく、サイクリングや釣りやキャンプ、その土地の風土や歴史、人との出会い……いろんなアクティビティや学びを織り交ぜながら、その人らしい体験ができるトレイルになっていくのが理想だよね」とルーカスは言う。
川面を眺めながら交わした言葉は、そのまま新しいトレイルのビジョンにつながっていく。
「今日は釣れないね」
「先行者がいるからね、、、」
「だけど、色々と話せて良かった」
釣りをしながら仲間たちと共有した数々のイメージは、これから少しずつ、このカツオトレイルに形となって刻まれていくのだ。

川との約束
この日はカツオトレイルからのアクセスの確認を兼ねた調査釣行。やがて竿をしまい、私たちはトレイルに戻った。魚影は薄く、思うような釣果には恵まれなかったが、それでも川は多くのことを教えてくれ、僕たちはそれに慕った。
今度は、もっとゆっくりと釣りに来よう。
時間に追われることなく、ハンモックを担いで旅をしながら釣りをする。山の稜線から湧き出た清流に身を委ね、一投一投に心を込めて。その日、川は僕たちを優しく受け入れ、アマゴも微笑んでくれるのではないだろうか。
カツオトレイルが描く海から山への物語に、釣り人たちの新たな章が加わっていく。ハンモックが森に揺れ、フライが渓流を舞い、焚き火が星空を照らす夜が来る。歩くこと、釣ること、そして語り合うこと。すべてが学びとなり、すべてが記憶となって、この道を歩く人々の心に刻まれていくことだろう。


カツオトレイルは、静岡県焼津市を起点に、静岡市、藤枝市、島田市を経て南アルプスの南端・川根本町を結ぶ、総距離205km・獲得標高6,150mの周回ルートです。駿河湾から南アルプスまでの豊かな自然を繋ぎ、海から山へと移り変わる景色を楽しむことができます。
「歩くことは学ぶこと」というトレイルラーニングの理念を軸に設計されたカツオトレイルでは、歩くことで五感を使い、土地や自然、地域文化とのつながりを再認識し、発見や学びを体験することができます。
2025年春より、セクション1から随時オープンを予定しています。
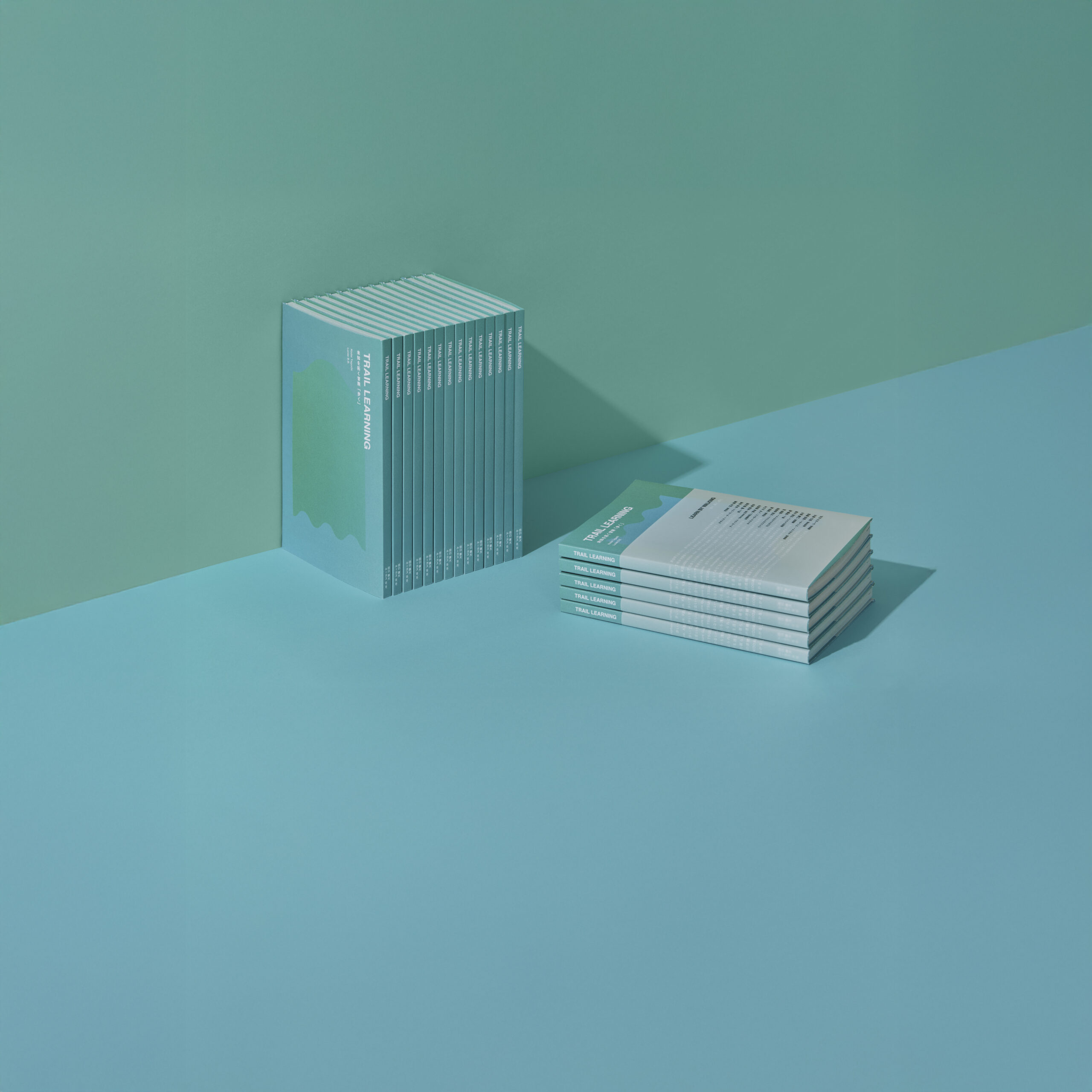
歩くことの可能性を再認識し、歩きながら学ぶことで自分の物語を紡ぐ。
本書は、世界で初めて「TRAIL LEARNING(トレイル・ラーニング)」をコンセプトに掲げた一冊です。
歩くことは単なる移動手段ではなく、人間の思考や創造性を深める行為です。古代ギリシャの哲学者たちは歩きながら議論を重ね、巡礼者たちは旅を通して自分自身と向き合ってきました。私たちもまた、歩くことで新たな洞察を得て、次の一歩を踏み出してきたのです。
本書の企画・編集は、ルーカス B.B.(『PAPERSKY』編集長)と田口康大(3710Lab代表)が手がけました。
デザイナーや詩人、アーティストなど13名のクリエイターが「歩くこと」の魅力を語り、歩くことが思考と創造を深める行為であることを探ります。
歩くことで得られる気づきやインスピレーションを通じて、自分自身の「歩く意味」を見つける1冊です。