
足元にいるクロダイを釣る
ひとつの釣りを
長くやる意味に気づいた
関西の地方都市からやってきた僕にとって、東京ほど過ごしやすい場所はない(魂を売り、すっかり標準語になった)。ただ、釣りとなると話は別だ。北海道の人から「車で5分の川で釣ったトラウトの話」や、静岡の人から「仕事を切り上げて夕マズメにサーフで釣ったヒラメの話」を聞くと居ても立ってもいられなくなる。しみじみうらやましくなる。

東京に住んでいると釣り場が遠い。トラウトもヒラメもアイナメも遠い。しかし、周りには湾奥でシーバスを狙う友人がいるし、カヤックを出して釣りをする親子もいる。車や電車で少し行けば外洋がある。暮らしの少し先に釣り場のある人たちが大勢いる。遠くを羨んで釣り場が遠いと、そう思い込んでいた。

自分の釣り場のある人たちは、自分の釣りをしているように思う。僕のようにあれこれ手を出さず(あんたいろいろやるねえと、釣具店の人に呆れられたことがある)、ひとつの釣りを繰り返しているように見える。そうすればおのずとその釣りの腕が上がるのではないか。釣りの基礎体力のある人は、ほかの釣りをやっても勘所を心得ている。しばらく同じ釣りを続け、自分の釣りを見つけてみるか。そんな大袈裟なことを考えて昨年末からシーバス釣りを再開した。

大都会の河川で竿を出すアンバランスな感覚もいいし、たまに釣れると楽しいものだ。職場のある高田馬場からも地下鉄を使えば湾岸エリアにすぐに出ることができる。自分が続けるのはこの釣りかと思った。春先になってバチ抜けのシーバス釣りを初体験した。バチ抜けなら誰だって釣れると聞き、専用ルアーを買い込んで、何度か川に行った。けれど、全く釣れなかった。腕が悪いのはわかるが、投資とリターンがまったく釣り合わない。金がかかりすぎる。
数度のボウズで何を言うか、技術も胆力もないとお叱りを受けそうだが、僕の知るシーバス釣りは道具と情報に縛られる(もちろん、上級者はそんなことはないだろうけれど)。どうやらこれは僕の釣りではないなと撤退した。もっと、自分に合った釣りはないのか。シンプルでエキサイティングな釣りはないのか。
豊洲で見つけた歩く釣り

豊洲に行く用事があり、ぐるり公園で夕景でも見ようと思った。散歩していると、大きなタモを腰に下げた釣り人を見かけた。ヘチ釣りか。これは岸壁や堤防の際(ヘチ)を狙って魚を釣る釣り方で、クロダイ狙いの人が多いそうだ。シーバス釣りをしていると、ヘチ釣り師たちが何処からともなく現れて、静かに竿を出して、何処かに消えていく光景に何度も出くわした。
彼を追うようにゆっくりと歩く。男性は仕掛けとともにカニを落とし、しばらく待っている。すぐに回収し、5メートルほど歩いてまた落とす。途中、ハシゴなどのストラクチャー周りは丁寧に攻めているようだった。オーバーハングになっているのか、少し沈めてはその奥に流していた。きっと、僕に見えていない海の表情が見えているのだろう。彼の装備はかなり軽装だった。これくらいならリュックひとつに全てが収まる。仕事終わりに竿を出すこともできるはずだ。ヘチ釣りに身軽さや自由さを感じた。
気がつくと、夕空が東京湾を染めていた。ねぐらへと帰る鳥が飛んでいる。東京にも大きな自然があるんだなと改めて感じる。もしかすると、この足元を探る釣りは自分のスタイルに合っているかもしれない。しばらくの間、ヘチ釣りを自分の釣りとしようか。

新しい釣りを始める楽しさ
友人の島本直尚君に連絡すると、おもしろそうだねという反応があった。シーバス釣りにのめり込んでいたなおさんもヘチ釣りが気になっていたようだ。しばらくすると、道具を揃えたという連絡が来た。早い。僕も揃えなければいけない。調べるとヘチ釣りの道具立てはとてもシンプルだった。3メートルほどの竿、ギアのないタイコリール、ライン、ガン玉、針。そしてタモ網だ。ほとんどシーバス釣りの道具を流用できそうだった。ただ、ラインの放出や巻き取りのしやすさ、また巻きクセの付きにくさなど、微細な変化を感知するタイコリールは必須のようだった。

池袋の釣具店でヘチ釣りをしたいので道具について伺いたいと尋ねると、若い店員さんの表情がふっと変わった気がした。「詳しい者を呼んできます」と店の奥に行く。しばらくすると、Oさんというスタッフが足早に近づいてきた。タイコリールの前にいる僕を確認すると「ヘチ釣りですか?」と笑顔になった。リールだけでなく、竿、ライン、針、重り、釣り方などを丁寧に説明してくれる。リールだけを買うつもりだったが、Oさんの話を聞いていると一式買った方が良さそうな気になった。
店に立つ人は身近な専門家だ。Oさんの説明からはヘチ釣り愛が溢れ出ていた。話を聞いているうちに、この人から道具を買いたいという気持ちになった。接客の最大の武器はそのジャンルへの愛だろう。会計後、「うれしいですよ、ヘチ釣りを始めてくれる人がいて」と言われた。釣具店でそんなことを言われたことがなかったので、まだ竿も出していないのに、この釣りが好きになった。しかし、新しい釣り道具の総額を見て軽いめまいを覚えた。
湾奥・雨後の濁川での対決

数日後、なおさんが調べた江東区の親水公園に向かった。都営住宅を通って運河に出ると、数日前の雨で濁りが入っていた。初夏だったが、川岸には風が吹き、涼しかった。
「この濁り、いいんじゃないかな」
「釣れる気しかしねーな」などと、初のヘチ釣りのくせにえらそうなことを言う。しかし、釣り人とは皆そうで、釣り場に入ったときの期待値は相当大きい。ベンチでセッティングをする。改めて購入したヘチ専用の継ぎ竿をじっと見る。細い。ラインはナイロンの2号、リーダーはフロロの1.5号、チヌ針は2号、ガン玉はBを打つ。「こんなに弱くて大丈夫なのかな」と不安になる。
屋形船が通り、波が岸壁まで打ち寄せてきた。この日は中潮で、満潮に向かって潮が上がるタイミングだった。柵から運河を観察する。ヘチ釣りのエサはミドリガイやフジツボなどを岸壁から採取するそうだけど、まだ壁に貝は付いていないようだったので、カニで釣ることにする。下から2番目の足に針を刺し、ふんどし辺りから針先を出す。これで完了。

一投目。竿の全長より50センチほど長く糸を出し、水面にそっとカニを着水させる。柵の上から腕と竿だけ出し、そのまま腕を落とす。クロダイは警戒心が強いので、水面を大きくのぞき込んだり、影を落とすと見切られてしまうそうだ。カニを自然にフォールしているように演出する。しばらく留め置いて引き上げる。そして、数歩移動して落とす、を繰り返す。道具だけでなく、釣り方もシンプルだ。それにしてもこんな町中にクロダイがいるのだろうかと、さっきの威勢が嘘のように不安になった。
二投目。針先がなにかに触れた気がした。すると、糸が沖に向かって大きく走った。慌てて合わせると、ブルブルブルっと震える。竿が大きく曲がる。この竿、こんなに曲がるのか。竿の肘当てを使って強い引きに耐える。しかし、クロダイの鈍く光る銀鱗を確認した瞬間、抜けてしまった。フッキングが甘かった。回収した針先を見るとカニがなくなっていた。 「やっぱ、いるんだ……」 しくじっても「魚がいる」ことがわかると俄然やる気が出てくる。ただ、引きが想像以上だったのが不安だった。この細い竿でクロダイを釣ることができるのだろうか。
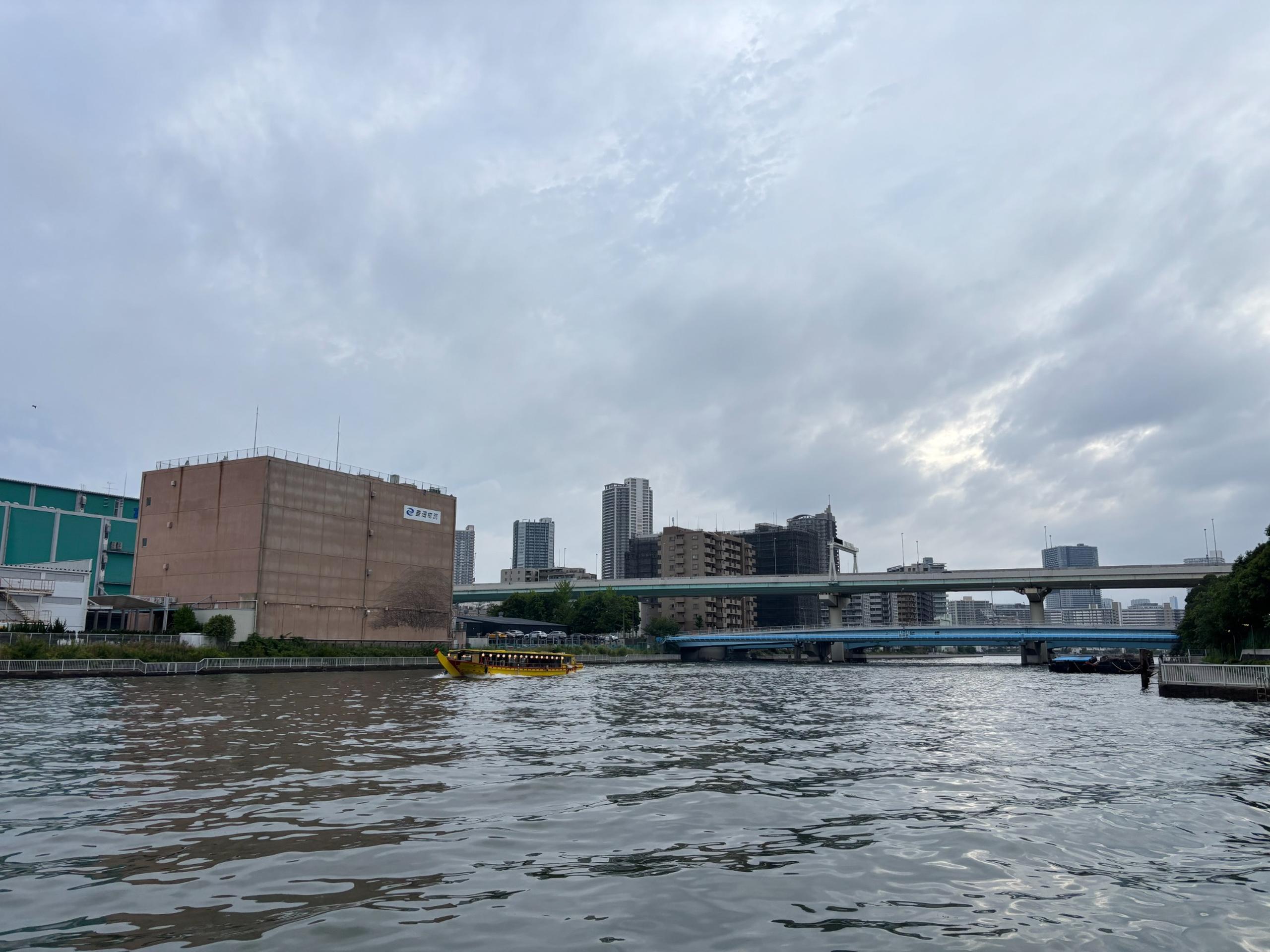
また船が通り、波がすぐ足元まで打ち寄せる。「釣りしてるー」と、僕らを見つけた女性の声が聞こえる。屋形船か。40メートルほど先からの声が聞こえるのだから、数メートル下のクロダイにも僕らの気配はわかるだろう。僕の気持ちまで読まれているのかもしれない。思ったより、繊細な釣りなんだなと改めて思った。ナイトクルーズのお姉さん、気付かせてくれてありがとう。
船が通り過ぎると波が打ち寄せる。じっと水面を見ていると三半規管が調整を始めて酔いそうになった。都会っ子すぎる。しかし、この釣りは船が通った後がいい気がした。波が水中をかき回すと、壁に付着した貝を落としたり、泥がかき回される。クロダイの活性が上がるのではないだろうか。見えもしない足元を想像し、カニを落としていく。
それから数投目。糸が沈みきらず止まった。水中をフォールしているはずのカニが止まっているということは……。一呼吸し、強く合わせると魚が乗った。魚は沖に、そして深く潜る。ここ最近、一番の引きに体の全細胞が喜びに沸き立つ。スプールを押さえていた親指を浮かせ、糸を出して魚を走らせる。川下に逃げる魚に合わせて動き、竿を立てて曲げる。さっきより引く。糸の放出を止め、竿を信じて大きく曲げ、反発を使って魚を浮き上げていく。耐えろ2号の道糸。糸を巻き、じりじりと魚との距離を詰めていく。手前まで寄せた竿がさらに弧を描く。なんて粘り強い竿なんだ。糸、切れるのかな。脳がネガティブシナリオを思い描き、先回りして失敗を想定している。だが、この防衛的悲観主義もクロダイの魚影をしっかり確認すると消えていった。二度、三度、クロダイが反転する度に鈍く刃物のように光る。やがて観念したクロダイが浮き上がった。クロダイはなかなかのファイターなんだな。タモを落とすと、観念したクロダイが頭からスッと入ってきた。

タモを引き上げると、手が震えていた。体内ではアドレナリンが出て、心拍も上がったのだろう。興奮と緊張のはざまで気持ちも高揚している。サイズは40センチほどだったけれど、魚の大きさではなく、狩りの喜びは身体の奥底から突き上げてくる本能的な高揚感だった。……ヘチ釣り、おもしろいじゃないか。
厚いクロダイだった。水墨の世界から飛び出したようなモノクロームの美しい魚体が、派手なレインボーのタモの中でえらを開きハアハアいっている。針を外しリリースしようとしていると、お年寄りが寄ってきて「ほほ、チヌですな」と言う。
「そうですね、チヌです。クロダイです」
「食べるんですか?」
「いえ、リリースします」
「せっかく釣ったのに、逃がすんですね」
「釣りをするんですか?」
「いえ、しないんです」
会話を続ける情熱もネタもなかったので、なんとなく「お近くですか?」と尋ねると、高層マンションを指差した。へえ、こんな近くにお住まいなら、釣り放題ですねと言うと、「ハハハ」と笑って去っていった。おじいさんも特に話すことはなかったようだった。
記念すべき初日は、クロダイを4匹釣ることができた。
それからヘチ釣りに行く度に数匹の釣果があった。行けば1〜2枚釣れるか、釣れないにしてもバラすとか、生命感のあるボウズだった。見事に何も起きることなく過ぎ去るシーバス釣りよりは、「釣れる釣り」だった。
週に一度は運河に行くことが習慣になった。釣具店のOさんに報告に行くと、我がことのように喜んでくれた。しかし、ある時4回連続でボウズを喰らってしまった。まるで釣れる気がしなくなった。釣りをしながら、延々と自問自答が始まる。何が悪いのだろう。フォールの速度か、針のサイズだろうか、何か悪い癖がついたのだろうか。考えつく限りいろんなことを試してみる。しかし、釣れない中でも「釣れない釣り」を楽しんでいる自分がいた。

池袋の釣具店に寄った時、Oさんに「釣れないんですよ」と相談すると、仕掛けやタイミングに対していろいろとアドバイスをくれた。そして最後にOさんはこう言った。
「それでも釣れないんだったら、そこには魚がいないんですよ。大丈夫です。魚がいたら釣れますから」
シンプルな言葉だが、真理だと思った。思えば、あれこれ手を出していた頃は絶えず、新しい釣り場、新しい道具、新しい技術。常に何かを求めていたように思う。週に数度通う豊洲の運河で、ほんの少しだけ魚の気持ちがわかるようになってきた気がする。ただ、「ほんの少し」だ。

しかし、この小さな発見の積み重ねが、僕の釣りを深くしていくように感じる。技術や道具ではなく、その場所との対話を重ねることで自分なりに見えてくる世界があった。
最近では移動で湾岸や運河近くを通る度、この辺りで竿が出せそうだなと考えるようになった。
テレビドラマで犯人を追うシーンでも水門や橋の下の影が気になる。
出張にはヘチ釣りの道具を持っていくことも増えた。仕事が終わった後、堤防でカニを捕まえてヘチを狙う。竿を出すと、ただ仕事で訪れただけの街でも違う姿が見えてくる。

遠くを羨む必要はなかった。北海道のトラウトも、静岡のヒラメも、東北のアイナメもきっと素晴らしいだろう。でも今の僕には、生活の延長や東京湾奥での釣りがある。高層ビルに囲まれた人工的な水路で、クロダイの銀鱗が光る瞬間を待つ。まさに自分の足元に釣りがあったのだ。


井上英樹(MONKEYWORKS)
編集者・ライター・温浴愛好家。兵庫県尼崎市出身。FISH UP編集部所属。最近はヘチ釣り以外に、サーフフィネスやロックフィッシュに引かれています。冬はスキーをしています。大好物はマンゴー(安い方)。


